読書感想文『日の名残り』カズオイシグロ
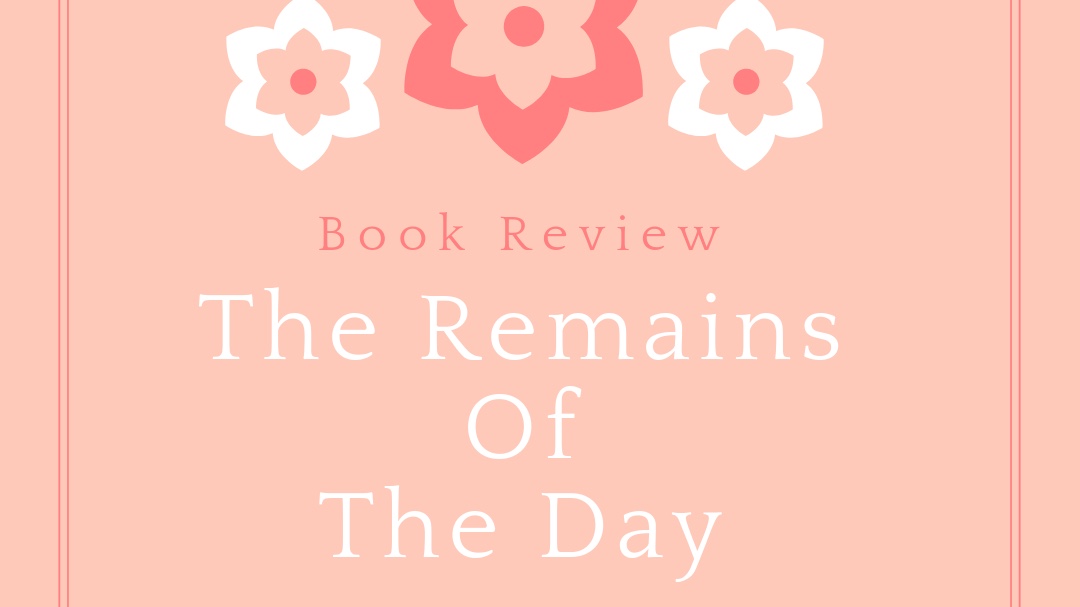
4月の半ばから6月の後半まで行っていた新婚旅行での発見。農業とか全く関係のない発見。
それは
キンドルめちゃくちゃ便利。
です。
僕は旅に出る前までは圧倒的に紙派でした。子供の頃からもちろん本は紙だし、大人になって電子書籍が増え始めてもやっぱり紙。電子書籍に移行する気配は自分の中では全くありませんでした。
が、長期の旅行となるとやはり持っていける本にも限りがあります。旅行中は移動中やちょっとした待ち時間などなど、以外とたくさん本を読む時間があります。それに部屋を掃除したり、料理を作ったり食器を洗う時間もなくなるからホテルでも本を読む時間が増えるんです。
なので1ヵ月半の旅行にもなるときっとたくさん本が欲しいなと。でも、たくさんは持っていけない。ということで電子書籍の中でもたぶんきっと一番有名なKindle paperwhiteを思い切って買ったんですが、もうこれがめちゃくちゃいい。
アフィリエイトサイトの雰囲気がでていますが、もうこれはマジでいい。
紙の本よりもサクサク読めるし、僕は先が気になって紙の本だと後半をちらっと読んでしまうんですがそれも面倒だからない。それに隅に何パーセント読んだのかが常時されるのもすごくいい。「あ、もう25パーセント読んだんだ」とか「99パーセントが終わるのが悲しいな。」とかとか。ページ数よりもいい。(それが嫌という人もいると思いますが消すこともできます。)それに暗いところでも読みやすいのもすごくいい。妻が眠たがってるけど僕はなんかまだ眠くない。そういう時に電気を消しても僕は本を読み続けられるし、ブルーライトもスマホなどに比べて少ないから、読むのをやめてもすぐに寝れる。
旅においてはいいことしかない。
悲しかったのは、旅に出る前に読んだ佐藤正午さんの『鳩の撃退法(上)』は紙の本だったのに、旅行中に続きをダウンロードしたものだから(下)はキンドルになってしまったということぐらい!!
そう、その時々の気持ちで読みたい本って変わるので、WiFi環境があればどこでもダウンロードできるっていうのもキンドルがメチャクチャいい理由の一つです。
と、アマゾンの営業はこれくらいにしておいて、久しぶりのブックレビューです。
イギリスにいた時に読んだのが『日の名残り』です。
昨年のノーベル文学賞を受賞した、長崎出身のイギリス人作家カズオ・イシグロさんの作品です。
以前『忘れられた巨人』を読みました。
リンクを飛んで読んでもらってもいいのですが、その感想は「この主人公が老夫婦じゃなくて、現世から異世界召喚されたニートとエルフのお姫様なら異世界ファンタジーラノベでアニメ化されてそう」です。
もうそれ以上でもそれ以下でもあるんですが、もうそれでいいです。はい。
今回「日の名残り」をイギリスで読んだのは、どうせイギリスで読むのなら、イギリスっぽい作品を読もうと思い、これほどイギリスで読むにふさわしい作品はないだろう!!と思ったから、で読んでみたらやっぱりイギリス、特にイギリスの田舎で読んでよかった。
これをもし大阪に旅行している途中とかに読んだら、まあ感情移入できないだろうことでしょう。
話のあらすじはいつも通り、僕がつらつらと書いても無駄なのでWikipediaを引用します。
物語は1956年の「現在」と1920年代から1930年代にかけての回想シーンを往復しつつ進められる。
第二次世界大戦が終わって数年が経った「現在」のことである。執事であるスティーブンスは、新しい主人ファラディ氏の勧めで、イギリス西岸のクリーヴトンへと小旅行に出かける。前の主人ダーリントン卿の死後、親族の誰も彼の屋敷ダーリントンホールを受け継ごうとしなかったが、それをアメリカ人の富豪ファラディ氏が買い取った。ダーリントンホールでは、深刻なスタッフ不足を抱えていた。なぜなら、ダーリントン卿亡き後、屋敷がファラディ氏に売り渡される際に熟練のスタッフたちが辞めていったためだった。人手不足に悩むスティーブンスのもとに、かつてダーリントンホールでともに働いていたベン夫人から手紙が届く。ベン夫人からの手紙には、現在の悩みとともに、昔を懐かしむ言葉が書かれていた。ベン夫人に職場復帰してもらうことができれば、人手不足が解決する。そう考えたスティーブンスは、彼女に会うために、ファラディ氏の勧めに従い、旅に出ることを思い立つ。しかしながら、彼には、もうひとつ解決せねばならぬ問題があった。彼のもうひとつの問題。それは、彼女がベン夫人ではなく、旧姓のケントンと呼ばれていた時代からのものだった。旅の道すがら、スティーブンスは、ダーリントン卿がまだ健在で、ミス・ケントンとともに屋敷を切り盛りしていた時代を思い出していた。
今は過去となってしまった時代、スティーブンスが心から敬愛する主人・ダーリントン卿は、ヨーロッパが再び第一次世界大戦のような惨禍を見ることがないように、戦後ヴェルサイユ条約の過酷な条件で経済的に混乱したドイツを救おうと、ドイツ政府とフランス政府・イギリス政府を宥和させるべく奔走していた。やがて、ダーリントンホールでは、秘密裡に国際的な会合が繰り返されるようになるが、次第にダーリントン卿は、ナチス・ドイツによる対イギリス工作に巻き込まれていく。
再び1956年。ベン夫人と再会を済ませたスティーブンスは、不遇のうちに世を去ったかつての主人や失われつつある伝統に思いを馳せ涙を流すが、やがて前向きに現在の主人に仕えるべく決意を新たにする。屋敷へ戻ったら手始めに、アメリカ人であるファラディ氏を笑わせるようなジョークを練習しよう、と。
これは純文学ではよくあることなのですが、この小説の中で特に何かがあるわけではありません。古くから(彼のお父さんも)執事を仕事にしていたスティーブンがかつての仕事仲間だったミス・ケントンに会いにいく道すがら昔のことを色々と思い出すだけの話です。
スティーブンが「昔はよかった」と必ずしもそういう言葉は使わないにしても、そう感じているのはひしひしと伝わってきます。それは仕方がないことです。なぜなら、彼の執事という職業自体が時代の中でだんだんと消えていく運命だからです。
スティーブンが務めていたダーリントンホール。かつてはヨーロッパの重要事項を陰で動かしていたと言っても過言ではないほどの重要な人物ダーリントン卿が持つお屋敷で、そこには日夜ヨーロッパの政治界に影響力を持つあの人やこの人やあのチャーチルやこのチャーチルが訪れては闊達に議論がされていました。ので、そこにいる執事もそれなりのプライドがあったわけです。
でも、ダーリントン卿は第二次世界大戦の前にナチスを支持するような姿勢を持ってしまっていたために、その後失脚します。
ダーリントン卿に関するスティーブンの語りには、なんとも言えない哀愁があります。かなり慕っていた主人が、だんだんと世間的に悪い評判をつけられ最後には悪評のまま亡くなります。支えていた執事としては悲しい話でしょう。でも、果たしてそうなのかと、ただ読んでいただけの僕らは思います。執事という対して政治のわからない人だから騙せていたけれど、やっぱりダーリントン卿は悪いやつだったのではないかとも思います。でもそういう議論さえも無駄なのです。そんなことを話すことすらできない、平和な時代にスティーブンはもう来てしまっているからです。
消えていく職業というのは以外とたくさんあります。今後もAIが普及すると会計に関わる人の数などが劇的に減っていくと言われています。昔の映画を見てみれば、偉い男の横には必ずと言っていいほど若い女性がいて、彼女は偉い男の言葉をタイプライターでポチポチと打ち込みます。
もうそんな人いません。職業がなくなるというのは当たり前のことなのだと思います。
だから、AIによって機械が人に代わり多くのところで働くようになり職を奪うと言われている今だからこそ、執事という普通に生きていたら全く関係を持つことのない職業の物語であっても、哀愁を共有してしまうのかもしれません。
この小説で最もひしひしと感じたことは「ゆっくりと衰退していくことの寂しさ」です。
この小説の中で「ゆっくりと衰退していく」物はたくさんあります。
まずはスティーブンの執事という職業。かつてよりも重要度がかなり下がり、今は新しい主人のファラディ様のお陰でなんとかスティーブンも執事を続けることができています。
そして二つ目はダーリントン卿。物語の中でダーリントン卿が失脚したことで、スティーブンの今のものさみしい生活があります。もしもダーリントン卿自体が衰退することがなかったとしても、スティーブンの仕事は遅かれ早かれ衰退していたでしょう。でも、やはりダーリントン卿の衰退からスティーブンの衰退も始まります。
三つ目はスティーブン自体。体も衰えていく中で、彼はある種の寂しさを感じています。家族もいない中でミス・ケントンに会いに言ったのはもう一度自分のところで女中として働かないかという思いがあるだけではなく、孤独な中で一瞬のつながりを感じたいという思いがあるのではないかと感じます。
スティーブンは仕事人間で家族もいません。そして一人で執事として支えながら老いていく彼に、執事という職業が消えていくこと以上の寂しさを感じました。
この小説は常になんとなくの哀愁があります。オールウェイズのように泣かせには来ないし、特に大問題が発生することもないけれど、ただなんとなくさみしい気持ちになる夜が誰にでもあるように、ただなんとなくの哀愁が漂っています。
読んだ後に明るい気持ちにも悲しい気持ちにもなりません。読んだ後に昔のもう二度と会わないであろう友達を思い出すみたいにちょっとだけ寂しい気持ちになります。




